 |
| 1.空襲体験 | 「生」の実感 創作の糧に |
| 一九四五(昭和二十)年三月、大阪上空に米軍機の大編隊が黒々とした姿を現し、焼い弾を浴びせ始めた。燃え上がる炎、渦巻く黒煙、逃げ惑う人々、折り重なる死体―。「だ…だれのせいだよ…こんな戦争…」。勤労動員先の工場から必死の思いで逃れた中学生は、行き場のない怒りに思わずつぶやいた。 |
手塚治虫は自伝的な作品「紙の砦(とりで)」や「どついたれ」で、自分が味わった死の恐怖を繰り返し、描いた。「目の前でわが子や父母の死を見なくてはならなかった人たちの、悪夢のような記憶を語って聞かせたい」。その胸には、戦争の悲惨さを訴える気持ちが、おき火のように燃えていた。
手塚より四つ年下の作家小田実(70)=西宮市=も同じ空の下にいた。疎開先の姫路から大阪に戻った翌日のことだった。
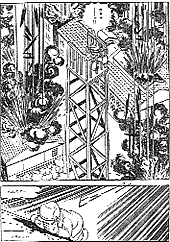 |
小田の手元には後年、米国で入手した空襲時の航空写真がある。大阪の大半を雲のような煙が覆っている。「きれいな眺めだろ」。小田は静かに言葉を継ぐ。「だが、この下は地獄だった。人がバタバタ死んでいった」
後にベトナム反戦運動に参加した小田は、大阪大空襲を「原点となる体験」と言う。爆撃機からは見えない世界。地上には、無理やり生をもぎ取られた市民がいる。彼らは永遠に、無念さを訴えることさえできない。
「だから、戦争は殺された側から語られねばならない。私と同じ視点を手塚さんは持っていた」 それぞれの国家の“正義”を振りかざした戦争が人々を破滅へと追い込む。その愚かさを、手塚は初期の「来るべき世界」から晩年の「アドルフに告ぐ」まで、一貫して表現し続けた。
終戦の日、手塚は「生きていてよかった」と心から思った。あと数十年は生きられる。好きな漫画を思いきり描ける。それは「最高の体験だった」と振り返る。
「その実感があるから、生命の尊さという理想を率直に掲げることができた」。同じ思いから平和の論理を紡いできた小田の目に、手塚は「自由をこよなく愛し、独裁を排する人」として映る。
手塚は最晩年のエッセーで「戦争の本当の姿を語り伝えていかなければ、再び、きな臭いことになりそうだ」と、不安を漏らした。彼の警鐘は二十一世紀の私たちに届いているだろうか。
◇ ◇ ◇
手塚治虫が最大のテーマとした「生命の尊さ」。その根底には、死と隣り合わせで過ごした思春期の強烈な体験がある。終戦記念日を前に、語り部として手塚が残した「戦争と平和」のメッセージに向き合ってみた。(敬称略)